- mode_commentコメント 3
-
知っちゃった - 可不・結月ゆかり
【思弁性のゲーミフィケーション、と化した思考。自問自答、大概、正気の沙汰でない状態。】
現代を取り巻く思想的人種的政治的分断、パンデミック、紛争と錯綜する中で陰謀論は急速に膾炙した。【超常現象を対象とした逆相の創造】及びその流布はゲーミフィケーションと呼ばれる構造を持つ。これはある事象に対して、複雑性を嫌い【分かりやすい構造を求め】る者が、無数の散らばる情報を集めて一つの明快な真実(と見せかけた陰謀)に辿り着くという、信者が同時に陰謀の創造者にもなる参加型構造である。この構造では責任の所在が不明の言明=【死んだディスクール】だけが独り歩きし、【超身勝手な解釈で妄想】が【権威性のある文系的意味論】を以て拡散されてしまう。
【カント以降の相関主義では例えば、相関の外部の実在を肯定する、一種のイデオロギーに対して、有効かつ不可逆的な反駁ができません。】
物自体は認識できずア・プリオリな形式認識とア・ポステリオリな判断の思惟の統合によって対象を直観するとしたカントの認識論は、それ以前の主体と客体の関係にコペルニクス的転回ともいわれる転倒を起こした。
その後フィヒテらはこれを批判的発展させ、主観と客観を切り離して考えることはできず、私たちが思考と存在の一方のみにアクセスするとはできないとする「相関主義」を展開した。この思想はフッサールやハイデガーら現象学や分析哲学など20世紀の思想の根底となっている。
相関主義においてはこうした陰謀論も存在として切り離すことができない。さらにはそうした思想に対して【シニシズムに至ることもまた、非合理の裏返しであって】、社会と自己の相関に絡めとられてしまう。相関の外部の実在を肯定することは「私は噓をついている」という言明と同じく語用論的矛盾を孕んでしまう。こうして自己に相関された【この社会の一部がもう、死んじゃった】のである。
デリダ以降、ハーマン、メイヤスー、グラント、ブラシエによるワークショップを端緒とする思弁的実在論は各々が別々の方向性で模索しつつ、相関主義からの脱却を目指す現代哲学の大きな潮流となっている。例えばメイヤスーは『有限性の後で』で「一次性質と二次性質についての理論(…)を立て直す時がきた」としてデカルトまで遡って思弁的唯物論を展開している。
思弁的実在論はまだ不完全な点も多い。しかしいずれ機能不全に陥った社会の次の根本原理となり新たな希望となることを願う。 -
死んでしまったんだ - 可不・結月ゆかり
【もしもコウモリの感情や、どこでもないところからの眺めに、本当にぼくらが触れられたのなら、どんなによかったでしょうか。】
トマス・ネーゲルは『コウモリであるとはどういうことか』で次のように述べている。
「たとえ私が徐々に形を変えていって、ついにはコウモリになることができるとしても、現在の私を構成している要素の中には、そのように変身した未来の私の状態の体験がどのようなものになるのかを、想像可能にしてくれるものは存在しないのである。」(勁草書房,p264)
コウモリを科学的に理解していてもそれは「生態」を知ることであって「コウモリである」ことではない。自己が自己である限り「コウモリである」ことはできないという【クオリアの私秘性】、ウィトゲンシュタインが「私は、私の世界である」「主体は、世界に属してはいない。それは、世界の限界なのだ」(『論理哲学論考』岩波文庫,5-63,5-632)と述べる、<私>は<あなた>にはなれないという究極的な【情報の非対称性】が自己と世界の間には横たわっている。その隔絶は疎外感を齎すが、同時に世界-内-存在としての自己を世界から切り離し、自己を規定する根拠として機能しうる。
では現代はどうだろうか。自由意志で選んだと思われた「趣味」が「階級」によって無意識的に決定されていることを『ディスタンクシオン』でブルデューが指摘したように、【ベンダーに狭められ】「自律」を奪われたフィルターバブルであたかも「自由な議論」の真似事をしているにすぎないのかもしれない。
【機械語が歩道を整備】した現代は議論という行為、情報すらも消費物となり、情報消費が目的化してゆく。<私>が希薄化した世界では、責任の所在も曖昧に【君の、吸い上げた記号でできた物語】がナラティブとして消費され、<私>としてではなく<全体>として還元されてしまう。こうして【想像と推測】が事実としてあたかも<私>と<あなた>を橋渡ししたかのように錯覚させる。
「自由と認識へと通じているかに見える行路の果てには、懐疑主義と無力状態が待ち構えている。わたしたちは、世界の内側からのみ行為できる。しかし、一方で、外側から自分を眺めれば内側から経験している自律は幻と化し、外側から見ているわたしたちには行為することなどまったくできない」(『どこでもないところからの眺め』春秋社,p196)
こうして事実は、自己は、【死んでしまった】のかもしれない。 -
ヘテロドキシー - 可不・flower
【創造に対する所感。ニーチェの言葉を専ら借用するならば、永劫回帰の中で既存の価値に囚われず、例えば、利己的に、独占的に、到達点を設定し得る芸術活動は、能動的ニヒリズムの確保に、有用な試行として期待される。】
Th.アドルノは『不協和音 管理社会における音楽』において複製技術の確立した世界での消費音楽を考察・批判している。そこでは音楽が「いま」「ここ」にのみ存在するというアウラから解体され、【品質が持つ価値は消えた】物象化と聴衆の退化に陥れるとして消費音楽の批判を展開している(ただしベンヤミンなどによる議論がある点は留意しなけらばならない)。
一方美学について、ハイデガーは1936年からの講義でニーチェの「力への意志」を美学の観点から考察している。この講義においてニーチェの芸術見解を五つの命題に整理した。
一、芸術は、力への意志の最も透明かつ周知の形態である
二、芸術は、芸術家の側から把握されねばならない
三、(…)芸術は一切の存在するものの根本的生起である(…)
四、芸術は、ニヒリズムに対する卓抜せる反運動である
五、芸術は「真理」よりも価値あるものである(近岡,2009)
『ツァラトゥストラかく語りき』でニーチェはキリスト教への異端=【ヘテロドキシー】として「神は死んだ」(河出文庫,pp17-18)と述べ救いを、「おのれ自身を、永遠を、回帰を、万物が永遠に同一であることを」(前同,p.555)と述べ生命の合目的性を全否定した。その絶対的な虚無主義においてとりわけ音楽が苦悩の超克に機能することは、ショーペンハウアーが『意志と表象としての世界』において「それ自体けっして直接的に表象せられ得ないところのある原型に対する模写なのである」(中公文庫,Ⅱ巻pp.206-207)として、アリストテレスが『詩学』で芸術の本質を「模倣」に帰しているように、音楽を意志の表象としての世界を最も模倣するものとしていることからも理解される。
音楽が消費物として飽和し【市場は破壊された】現代であっても、意志の表象としての【成果物以外の浸潤を排し】自らの信じる美学を絶対的に肯定することが「超人」への道なのかもしれない。
出典
近岡資明「ハイデッガーのニーチェ解釈における美学との対峙」広島芸術学会,Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts,21・22巻,pp57-71
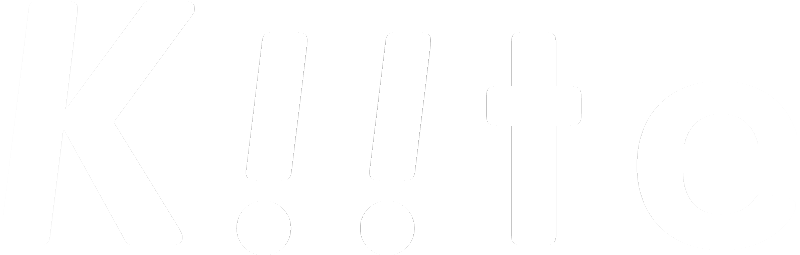
ログインするとコメントの閲覧・投稿ができるようになります